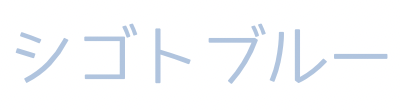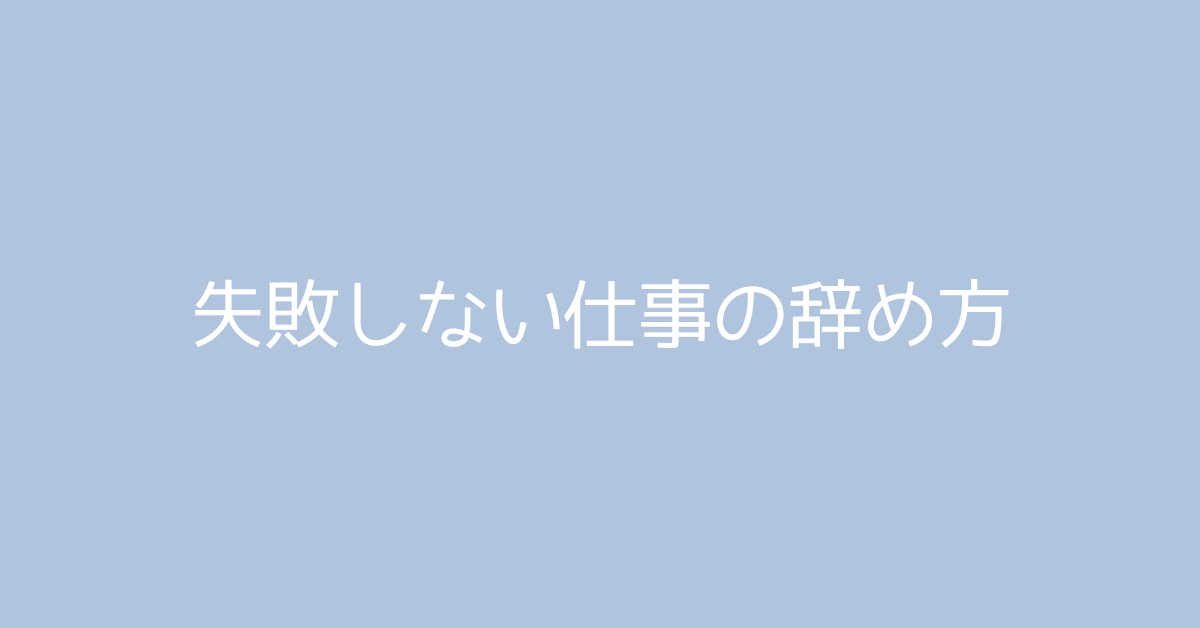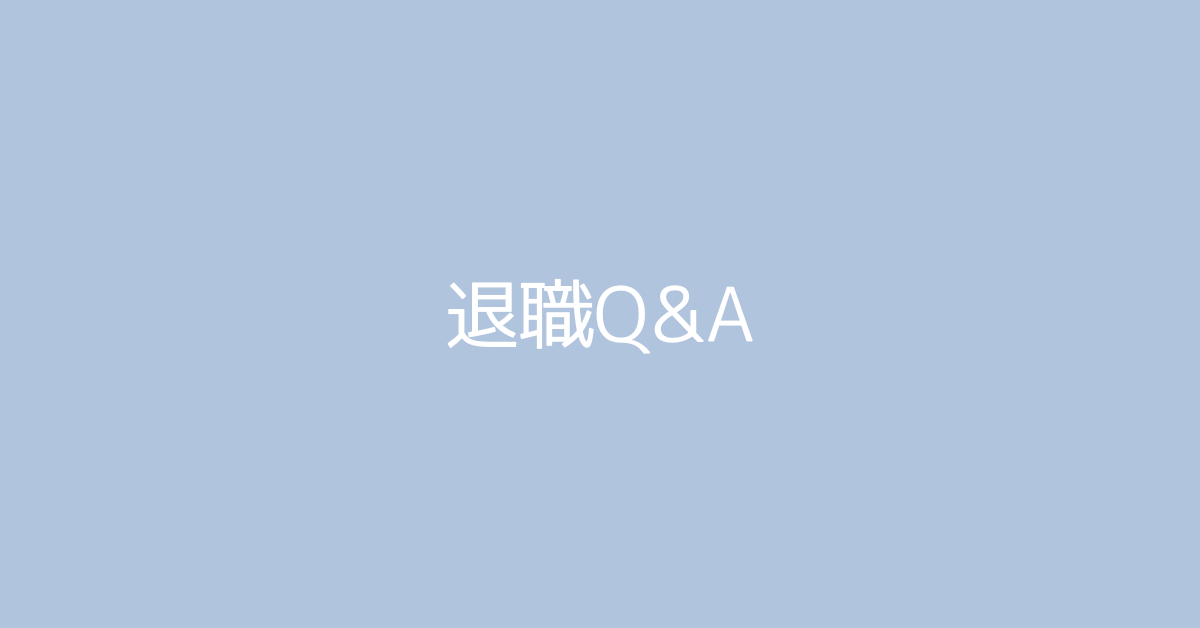仕事の辞め方ロードマップ
【STEP1】退職したい理由を洗い出す
▼
【STEP2】就業規則を確認する
▼
【STEP3】次の仕事を確保する
▼
【STEP4】退職意思を伝える
▼
【STEP5】退職願(退職届)を提出する
▼
【STEP6】引継ぎ・挨拶回りはしっかりと
▼
【STEP7】貸与品の返却、退職書類を受け取る
【STEP1】退職したい理由を洗い出す
まずは「退職したい理由」を洗い出すことから始めましょう。
→やりたい仕事が見つかった、給料が安い(年収を上げたい)、労働環境がブラック(ホワイトに働きたい)、在宅勤務したいなど、色々あると思います。
次の仕事では、これらの不満を1つでも多く解消するために、辞めたい理由を全部書き出しておきましょう。
併せて、いつ頃までに退職したいのか、今すぐ退職したいのかなど、退職したい時期の確認もしておきましょう。
【STEP2】就業規則を確認する
正社員の場合、民法では「退職の2週間前までに退職意思を伝えれば退職できる」ことになっています。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(契約社員や派遣社員などの有期雇用の場合、年棒制の場合など、例外あり)
ただ、退職の2週間前の申し出だと、後任や引き継ぎが間に合わないので嫌がられたり、場合によっては怒られたりと、デメリットが多いので、円満退職するためには就業規則に沿って退職したほうが良いです。
会社の就業規則を確認して、退職時の申し入れ時期や、必要な手続きを確認します。会社によって変わりますが、「退職の1か月前~3か月前までに申し出ること」と書かれていることが多いです。
併せて、就業規則で退職金の支給条件も確認しておきましょう。退職時期を決める参考にもなります。
【STEP3】次の仕事を確保する
体調不良などのやむを得ない理由で「どうしても今すぐ辞めたい」という場合を除いて、次の仕事を確保してから辞めましょう。これ、かなり超重要です。
理由は、無職の状態で転職活動すると不利だからです。書類選考や面接の通過率が悪くなったり、転職活動が上手くいかないことの焦りや、収入が途絶えることによる不安などから、「とりあえず早く仕事をしないとマズい…」と妥協して仕事を決めることになり、失敗するリスクが上がります。
そもそも「今の仕事を辞めたい理由」を解消できないと、本末転倒になってしまいます。
なので、できる限り転職先を決めてから辞めましょう。
転職の手順は転職Wが参考になります。
※どうしても次の仕事が決まる前に辞めたい時には
やむを得ない事情などで、どうしても次の仕事が決まる前に辞めたい場合は、次の手順を検討してみてください。
①まずは有給を使って休む、転職活動を進める
②体調不良なら、休職を相談する
③退職後3か月~半年は生活できる状態にしておく(貯金、節約など)
※とにかく在籍期間を伸ばすこと、それもダメな場合は、退職後の生活費を確保してから辞めることが重要です。場合によっては、実家に戻るなども検討しましょう
【STEP4】退職意思を伝える
直属の上司に「いつ退職したいのか」を伝えます。
確実に辞めるために、相談ではなく、「退職意思が固まった報告」として伝えましょう。退職希望日は、残りの有給消化日数、引継ぎのスケジュールなども踏まえて伝えます。
退職理由は「他にやりたい仕事が見つかった」などポジティブな理由で伝えるか、やむを得ない理由で伝えるのが定石です。会社の不満を言ったり、転職先のことを言うと、引き止められたり、退職までの残りの期間の風当たりが強くなる、思わぬトラブルになるなど、デメリットが生じます。
※退職意思を伝えるタイミングは、2か月〜1か月半くらい前で、できれば、業務に支障が出ない時期や時間帯など、上司が落ち着いているタイミングで伝えるとスムーズです
※上司が嫌で直接言えない場合は、上司の上司、人事などに伝えましょう
※会社の人と接触するのに拒否反応がある場合は、退職代行を検討しましょう
【STEP5】退職願(退職届)を提出する
会社の規定に従い、退職願(または、退職届)を作成し、提出します。
退職願(退職届)が不要な場合や、書式が決まっている場合があるので、会社に確認して指示に従いましょう。
【STEP6】引継ぎ・挨拶回りはしっかりと
「飛ぶ鳥跡を濁さず」を意識しましょう。スムーズに退職するために、引継ぎ・挨拶回りはしっかりと。
自分的に重要な人とは連絡先を交換しておいて、今後もつながれるようにしておくと、今後の仕事やキャリアに役立ちます。
最終出社日には、社内のお世話になった人に、直接会えるなら対面で、会えない人にはメール・チャットなどで感謝の気持ちを伝えましょう。
※社外への挨拶のタイミングなど、上司に確認しましょう
※任意でお菓子などを渡しても良いです
※退職が決まると、プレッシャーからの解放感や、気の緩み、やる気を失って仕事の質が落ちることがありますが、信頼関係が落ちないように、最終出勤日まで気を引き締めておきましょう
【STEP7】貸与品の返却、退職書類を受け取る
最終出勤日など、退職時には、会社から借りている物の返却と、退職書類を受け取ります。
●退職時に返却するもの
・健康保険証
・社員証
・名刺
・貸与パソコン
・書類、データなど
●退職時に受け取る書類リスト
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・健康保険資格喪失証明書
・高額療養費の限度額適用認定証(使用していた場合)
・年金手帳(または基礎年金番号通知書。マイナンバー管理の場合もあり)
・離職票(次の仕事が決まっていないなど、希望時)
・最後の給与明細
・退職金の支給明細(支給時)
・在職証明書(希望する場合)
・退職証明書(希望する場合)
・会社保有の個人の資格や免許証(あれば) など
これらの書類を受け取ったら、退職日や離職理由などが正しいか確認しましょう。また、次の会社の手続き、役所の手続きなどに必要になるので、無くさないようにしっかり保管しておきましょう。
退職後に届く書類(離職票、源泉徴収票など)もあるので、受け取るタイミングを事前に確認しておきましょう。
※次の仕事が決まっていない状態で先に辞める場合の手続き
転職先が決まっていない状態で先に辞める場合は、以下の手続きをします。
・健康保険の手続き(任意継続、または、国民健康保険に切り替える)
・年金の種別変更(国民年金などに切り替える)
・失業給付の申請(自宅エリア管轄のハローワークに離職票を提出)
チェックリスト
最後に、この記事で紹介した内容のチェックリストです。
⬜︎ 退職したい理由を洗い出す
⬜︎ 就業規則を確認する
⬜︎ 次の仕事を確保する
⬜︎ 退職意思を伝える
⬜︎ 退職願(退職届)を提出する
⬜︎ 引継ぎ・挨拶回りはしっかりと
⬜︎ 貸与品の返却、退職書類を受け取る
※今回は一般的な退職の手順を紹介しました。個別のケース事例や、法律的な疑問などは、会社、役所(、場合によっては弁護士)など、専門の人に確認するのが安心です
後悔しない退職ができることを願っています。